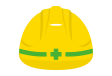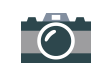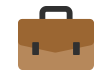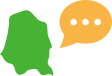国民年金
国民年金
国民年金とは
20歳以上60歳未満のすべての方が加入する必要がある公的な制度になります。
年金の加入期間中に保険料を納めることで将来受け取れる年金の受給資格や年金額に算入されるようになります。
加入の種類
|
第1号被保険者 |
20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生等 納付書や口座振替等によって保険料を納めるようになります。 ※年金の加入は役場で手続きが必要になります。 |
|---|---|
|
第2号被保険者 |
会社員や公務員等 厚生年金の手続きはお勤め先の事業所で手続きが必要になります。 |
|
第3号被保険者 |
20歳以上60歳未満の厚生年金や共済組合に扶養されている配偶者。 ※第2号被保険者のお勤め先経由で手続きが必要になります。 |
国民年金の保険料
|
保険料 |
【月額】16,520円 (令和5年度) ※年金の支払いを前納することで年金額が割引になります。 (6か月前納、1年前納、2年前納)の種類があり、前納する期間が長いほど割引料金も増えます。 付加保険料:年金の保険料に加算してお支払いができます。 |
|---|
年金保険料の口座振替・クレジットカード支払いについて
1,口座振替でのお支払い
口座振替は、ご指定の金融機関の預金口座から、定期的に国民年金保険料を振替して納付する方法です。口座振替で納付すると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。また、まとめて前払い(前納)すると国民年金保険料が割引されます。
振替方法
口座振替の振替方法は、次の5種類です。
国民年金保険料は、まとめて前払い(前納)すると割引が適用されるのでおトクです。
- 2年前納
4月分から翌々年の3月分までの2年分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。 - 1年前納
4月分から翌年の3月分までの1年分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。 - 6カ月前納
4月分から9月分まで、10月分から翌年の3月分までの6カ月分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。 - 当月末振替(早割)
毎月の国民年金保険料を納付期限よりも1カ月早く振替する方法です。 - 翌月末振替
毎月の国民年金保険料を納付期限である納付対象月の翌月末日に振替する方法です。(割引なし)
振替方法ごとの納付額・割引額・振替日
|
振替方法
|
2年前納
|
1年前納
|
6カ月前納
|
当月末振替(早割)
|
翌月末振替
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1回あたりの納付額
|
385,900円
|
194,090円
|
97,990円
|
16,470円
|
16,520円
|
|
割引額
|
16,100円
|
4,150円
|
1,130円
|
50円
|
ー
|
|
振替日
|
4月末日
|
4月末日
|
4月末日および10月末日
|
納付対象月の当月末日
|
納付対象月の翌月末日
|
※1回あたりの納付額は令和5年度の金額です。
※2年前納、1年前納、または6か月前納(4月~9月分)を選択した場合は3月分、6か月前納(10月~翌年)
口座振替の手続き方法
提出する書類:国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書
提出時期:2年前納、1年前納、6か月前納(4月~9月)を申し込む場合は2月末日必着。6か月前納(10月~3月)の場合は8月末日までに申し込む必要があります。当月末振替(早割)や翌月末振替を希望する場合はいつでも申しむことが可能です。
提出先:振替口座のある金融機関の窓口またはお近くの年金事務所(年金事務所への提出は、窓口のほか郵送による手続きも可能です。)
口座振替による納付をやめるときの手続き・振替停止月
提出する書類:国民年金保険料口座振替辞退申出書
提出先:振替口座のある金融機関の窓口またはお近くの年金事務所
振替停止月:手続した月以降に停止となります。
※さらに詳しい内容については日本年金機構ホームページをご確認ください。
2,クレジットカードでのお支払い
ご指定のクレジットカードから定期的に国民年金保険料を納付する方法です。
クレジットカードで納付すると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。また、まとめて前払い(前納)すると国民年金保険料が割引されます。
※国民年金が免除等されている方はクレジット払いができませんのでご注意ください。
※カード番号等に誤りがあると、手続きが間に合わない場合がありますのでご注意ください。
納付方法
クレジットカードによる納付方法は、次の4種類の方法があり、クレジットカード会社が立替納付します。
国民年金保険料は、まとめて前払い(前納)すると割引が適用されるのでおトクです。
- 2年前納
4月分から翌々年の3月分までの2年分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。 - 1年前納
4月分から翌年の3月分までの1年分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。 - 6カ月前納
4月分から9月分まで、10月分から翌年3月分までの6カ月分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。 - 毎月納付
毎月の国民年金保険料を納付対象月の当月末日に納付する方法です。(割引なし)
納付方法ごとの納付額・割引額・立替納付日
|
納付方法
|
2年前納
|
1年前納
|
6カ月前納
|
毎月納付
|
|---|---|---|---|---|
|
1回あたりの納付額
|
387,170円
|
194,720円
|
98,310円
|
16,520円
|
|
割引額
|
14,830円
|
3,520円
|
810円
|
ー
|
|
立替納付日
|
4月末日
|
4月末日
|
4月末日および10月末日
|
納付対象月の当月末日
|
クレジットカードによる納付の手続き方法
提出する書類:国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書
提出時期:2年前納、1年前納、6か月前納(4月~9月)を希望する場合は2月末日。6か月前納(10月~3月)を希望する場合は8月末日までにお申し込みが必要となります。毎月納付を希望する場合はいつでも申し込むことができます。
提出先:平田村役場またはお近くの年金事務所(年金事務所への提出は、窓口のほか郵送による手続きも可能です。)
クレジットカードによる納付をやめるときの手続き・停止月
提出する書類:国民年金保険料クレジットカード納付辞退申出書
提出先:平田村役場またはお近くの年金事務所
納付停止月:手続した月以降に停止となります。
※クレジットカード会社の規定により会員資格を喪失した場合はクレジットカード納付が停止となりますのでご注意ください。
年金を納めることが難しい場合
学生の方や所得が低い方など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人の申請手続きによって保険料の納付が免除(全額または一部)または猶予される制度があります。
(一般の方が対象となる免除・納付猶予申請、学生の方が対象となる学生納付特例申請があります。)
保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)を受け取れます。(手続きをされずに未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)
保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は以下の表のとおりです。その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。
|
|
老齢基礎年金の
受給資格期間への算入 |
老齢基礎年金の
年金額への反映 |
障害基礎年金、
遺族基礎年金の 受給資格期間への算入 |
|---|---|---|---|
|
納付
|
あり
|
あり
|
あり
|
|
全額免除
|
あり
|
あり
(※2) |
あり
|
|
一部納付
(※1) |
あり
|
あり
(※3) |
あり
|
|
納付猶予
学生納付特例 |
あり
|
なし
|
あり
|
|
未納
|
なし
|
なし
|
なし
|
※一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
※年金額への反映の割合については、下記「保険料免除・納付猶予された期間の年金額」をご覧ください。
保険料免除・納付猶予された期間の年金額
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
- 全額免除
保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。 - 4分の3免除(納めた保険料額 4,130円:令和5年度)
保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます。 - 半額免除(納めた保険料額 8,260円:令和5年度)
保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)が支給されます。 - 4分の1免除(納めた保険料額 12,390円:令和5年度)
保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が支給されます。 - 納付猶予制度
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
※過去期間は2年1か月前まで申請できますが、申請が遅れたり未納のままにしておくと、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けれない場合がありますのでお早めに申請してください。
申請方法
申請先:平田村役場またはお近くの年金事務所
必要書類:基礎年金番号かマイナンバーの分かる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード等)
※学生納付特例を申請される方は上記の書類のほかに学生証のコピーまたは在学証明書の原本が必要となります。
老齢年金
|
老齢年金の受給要件 |
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。 注) 保険料が一部免除の方の場合は、一部の保険料を納めないと未納扱いになりますのでご注意ください。 |
|---|
|
老齢年金の受給開始時期 |
原則として65歳からの受給が可能です。65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。 また、60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰り上げ受給」や66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰り下げ受給」を選択することができます。 ※昭和27年4月1日以前生まれの方、または平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰り下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。 |
|---|
|
老齢年金の受給額 |
【令和5年度】 795,000円(満額) (月額66,250円) |
|---|
障害基礎年金
|
障害年金の受給要件 |
1,障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。 ・国民年金加入期間 ・20歳前または、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間 2,障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。 3,初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3/2以上あること。 ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。 |
|---|
※上記の1から3のすべてを満たさないと障害年金が支給されませんのでご注意ください。
|
障害基礎年金の請求時期 |
1,障害認定日による請求 障害認定日に法令に定める障害に状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達しときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。 なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により5年分が限度です。 2,事後重症による請求 障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。 ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。 なお、請求した日の翌月分から受取となりため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。 |
|---|
|
障害基礎年金の年金額 |
【令和5年度】 1級→993,750円+子の加算額※ 2級→795,000円+子の加算額※
※子の加算額 2人まで・・・1人につき228,700円 3人目以降・・・1人につき76,200円 |
|---|
遺族年金
国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
|
遺族基礎年金の受給要件 |
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。 1,国民年金の被保険者である間に死亡したとき 2,国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき 3,老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき 4,老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき |
|---|
|
遺族基礎年金の受給対象者 |
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。 なお、遺族厚生年金を受給できる遺族の方は合わせて受給できます。 1,子のある配偶者 2,子 ※こどもは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方を指します。 ※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子に遺族基礎年金は支給されません。 |
|---|
|
遺族基礎年金の受給額 |
【令和5年度】 795,000円+2人目以降の子の加算額 1人目および2人目の子の加算額 各228,700円 3人目以降の子の加算額 各76,200円 |
|---|
年金各種届出書の電子申請(マイナポータル)
マイナポータルは、子育てや介護の手続きなどを電子申請でワンストップでできる自分専用のポータルサイトになります。年金の場合は、国民年金の資格取得(種別変更)の届出、国民年金の保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請の電子申請が可能です。
詳しい概要や申請方法等については日本年金機構ホームページをご確認ください。
電子申請(マイナポータル)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)<外部リンク>
関連リンク
各種年金手続きについて日本年金機構ホームページをご確認ください。
各種年金手続き時の準備資料等を事前に確認及び年金相談の事前予約などご利用いただけます。
◆日本年金機構のページはこちら
https://www.nenkin.go.jp/<外部リンク>
◆全国国民年金基金のページはこちら
https://www.zenkoku-kikin.or.jp/<外部リンク>
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
Copyright (C) Hirata Village All Rights Reserved