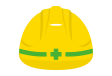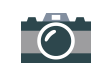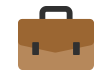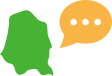河川水質検査
河川の水質を検査しています
村内の主要河川について水質調査の現況、経年変化について調査することで、水質汚濁の防止を図っています。
水質検査項目
- 水素イオン濃度(pH)
pHは、水の酸性、アルカリ性の度合いを表す指標です。
pHが7の時は中性で、それより大きいときはアルカリ性、小さいときは酸性になります。
河川水は通常7付近ですが、海水の混入、温泉水の混入、流域の地質(石灰岩地帯など)、人為汚染(工場排水など)、植物プランクトンの光合成(特に夏期)などにより酸性あるいはアルカリ性になることがあります。
- 生物化学的酸素要求量(BOD)
BODは溶存酸素(DO)が十分ある中で、水中の有機物が好気性微生物により分解されるときに消費される酸素の量のことをいいます。
有機物汚染のおおよその指標になりますが、微生物によって分解されにくい有機物や、毒物による汚染の場合は測定できません。逆にアンモニアや亜硝酸が含まれている場合は微生物によって酸化されるので、測定値が高くなる場合があります。
BODが高いとDOが欠乏しやすくなり、BODが10mg/L以上になると悪臭の発生などが起こりやすくなります。
- 化学的酸素要求量(COD)
化学的酸素要求量は、被酸化性物質(主として有機物)を、酸化剤を用いて一定の条件のもとで酸化するときに消費される酸化剤の量を、酸素の量に換算したものです。
酸化剤によって酸化される物質には無機物もありますが、大部分は有機物ですので、有機物による水質汚濁の指標となっています。
また、工場排水の指標としても用いられています。
- 浮遊物質量(SS)
浮遊物質は水中に浮遊または懸濁している直径2mm以下の粒子状物質のことで、粘土鉱物による微粒子、動植物プランクトンやその死骸、下水、工場排水などに由来する有機物や金属の沈殿物が含まれます。浮遊物質が多いと透明度などの外観が悪くなるほか、魚類のえらがつまって死んでしまったり、光の透過が妨げられて水中の植物の光合成に影響することがあります。
- 大腸菌群数
大腸菌群数は、大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌の数のことをいいます。水中の大腸菌群数は、し尿汚染の指標として使われています。
- 全窒素・全リン
窒素やリンは、植物の生育に不可欠なものですが、大量な窒素やリンによる富栄養化が進むと、植物プランクトンの異常増殖を引き起こす原因にもなります。
- 流量
流量は、河川を流れる水の量を測定しています。
水質検査結果
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
Copyright (C) Hirata Village All Rights Reserved