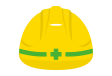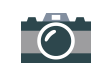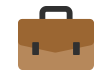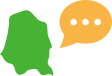令和6年度児童手当制度改正のお知らせ
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となります。
主な制度変更点は次の4つです。
1、支給対象期間が高校生年代まで延長されます。
支給対象となる児童が、現行の「0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学校修了前)の間にある日本国内に居住する児童」から、「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)の間にある日本国内に居住する児童」となります。
2、所得制限が撤廃されます。
現在設けられている所得制限・所得上限が撤廃され、所得額が所得制限限度額以上で特例給付を受給されていた方や所得上限限度額以上で手当を受給していない方についても、児童手当の支給となります。
ただし、所得制限撤廃後も、父母など2人以上の者が同一の児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする場合には、これらの方のうち「生計を維持する程度が高い者(原則所得の高い方)」が受給者(請求者)になります。
※「監護」とは、児童の生活について社会通念上必要とされる監督、保護を行っている(面倒をみている)ことを示します。
3、第3子以降の支給月額が30,000円に増額されます。
現行制度では「3歳以上小学校修了前までの児童のうち第3子以降の児童については月額15,000円の支給」でしたが、「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する児童のうち第3子以降の児童ついては月額30,000円の支給」となります。
※多子の数え方は、受給者が監護・養育等をしている0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子以降と数えます。(令和6年9月30日以前については0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にいる児童のうち年長者から数えます。)
※18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代)を多子としてカウントするためには、「①監護に相当する世話等をしていること、②生計費の負担をしている」ことの2点の要件を満たす必要あります。(例:子の学費を負担している、別居の子に生活費の仕送りをしている、同居で食費等の負担がありこれを欠くと通常の生活水準が維持できない等)
4.支給月が年6回になります。
支給月が年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)となります。
※ただし、令和6年度については年度途中の令和6年10月(12月支給分)から制度が変更になるため、6月、10月、12月、2月の4回です。
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
Copyright (C) Hirata Village All Rights Reserved